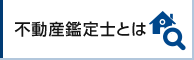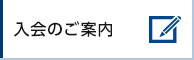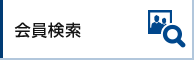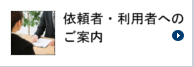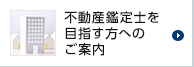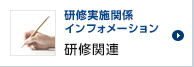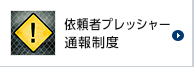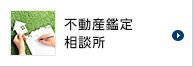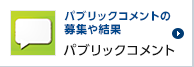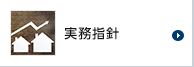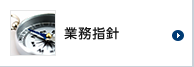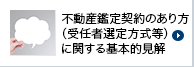Q7.共有取得物の分割法
Q7.
兄弟3人で父母の自宅を相続で共有取得したのですが、長男が単独所有として住みたいと言い出したが話し合いがつかない。共有物分割にはどのような方法があるのでしょうか。
A7.
不動産の相続による分割には①売却して売却代金を分割する「換価分割」、②不動産を相続した人が他の相続人に現金などを支払う「代償分割」、③売却も分割もせず相続人全員での「共有」、④不動産をそのままの状態で分割する「現物分割」があり、それぞれ一長一短があります。
換価分割(①)は自宅を売却して、売却代金を共有持分で公平に分けられますが、売却物件としての市場性、希望価格での売却が難しい難点があります。代償分割(②)は相続不動産を残し、公平に分けることが可能ですが、代償金の前提となる不動産の時価を巡ってもめることも多く、また不動産を相続する人に代償金負担に見合った資金的余裕が求められます。共有(③)は相続不動産を残せる、公平に分けることが可能で資金も必要ありませんが、不動産の処分(売却)や維持(建替え、増改築)に共有者全員の同意が必要であり、時間の経過による世代交代と共に共有者が増大しトラブルが拡大する恐れが残ります。現物分割(④)は不動産を残せますが分割可能な不動産でなければなりません。
前記分割方法のうち、本問のケースでは長男が自宅を単独取得するので代償分割による解決です。しかし、当事者間における現実の話し合いの場ではそれぞれの思惑に沿った各種資料が持ち込まれて、価格についての主張が交錯し代償金算定の基礎となる不動産の時価を巡って混乱することが多く見られます。
不動産に関わる共有物分割は遺産分割のほか遺留分減殺請求、夫婦間の財産分与など色々な場面が予想されますが、不動産鑑定士調停センターでは公正中立な評価によって話し合いによる解決を期待することができます。
換価分割(①)は自宅を売却して、売却代金を共有持分で公平に分けられますが、売却物件としての市場性、希望価格での売却が難しい難点があります。代償分割(②)は相続不動産を残し、公平に分けることが可能ですが、代償金の前提となる不動産の時価を巡ってもめることも多く、また不動産を相続する人に代償金負担に見合った資金的余裕が求められます。共有(③)は相続不動産を残せる、公平に分けることが可能で資金も必要ありませんが、不動産の処分(売却)や維持(建替え、増改築)に共有者全員の同意が必要であり、時間の経過による世代交代と共に共有者が増大しトラブルが拡大する恐れが残ります。現物分割(④)は不動産を残せますが分割可能な不動産でなければなりません。
前記分割方法のうち、本問のケースでは長男が自宅を単独取得するので代償分割による解決です。しかし、当事者間における現実の話し合いの場ではそれぞれの思惑に沿った各種資料が持ち込まれて、価格についての主張が交錯し代償金算定の基礎となる不動産の時価を巡って混乱することが多く見られます。
不動産に関わる共有物分割は遺産分割のほか遺留分減殺請求、夫婦間の財産分与など色々な場面が予想されますが、不動産鑑定士調停センターでは公正中立な評価によって話し合いによる解決を期待することができます。