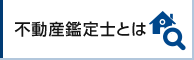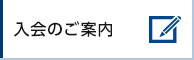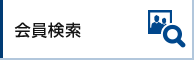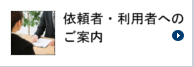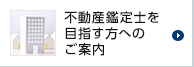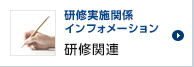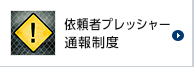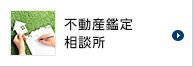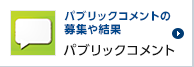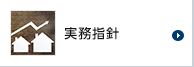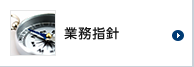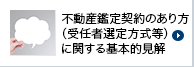業務指針に関するQ&A
所掌委員会:業務委員会
<質疑応答集をご参考と頂く際の注意事項>
会員から寄せられた質問、及びその回答を元にQ&Aを作成しております。
質問に当たりご提示頂きました前提条件・背景・状況等を踏まえ、当委員会にて把握又は推定可能な範囲内で回答等を行っております。
特段の記載がない限り、回答時点に適用されている業務指針等に照らして回答等を行っております。
そのため、回答内容は過去又は将来において不変的に適用されるものではありません。
不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針
役割分担
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H25.9 | 記名不動産鑑定士の審査鑑定士兼務 |
| H25.9 | 業務提携における契約書面の必要性と例外 |
| H25.11 | 一人業者が一部再委託した場合の受託審査及び報告書審査(証券化以外)兼務 |
| H26.1 | 役割分担及び業務提携 |
| H26.7 | 役割分担表の鑑定評価書への必要性 |
| H26.8 | 業務提携のひな型文書 |
| H26.12 | 不動産鑑定士1名事務所の役割分担表 |
| H28.1 | 提携業者の鑑定評価書の保管義務業者 |
| H28.2 | 事例収集の業務提携及び評価書の保管 |
| H28.3 | 報告書の審査と署名不動産鑑定士の役割分担 |
| R1.10 | 総括不動産鑑定士が確定担当鑑定士の場合の実査 |
| R3.9 | 不動産鑑定評価報告書のレビュー |
| R4.1 | 役割分担表の省略 |
| R5.6 | 役割分担(財務諸表) |
| R5.8 | 業務提携(REA-Jirei) |
| R6.4 | 署名不動産鑑定士の審査鑑定士兼務 |
| R6.5 | 個人鑑定士の審査鑑定士兼務 |
再委託等
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H25.12 | 鑑定業務の一括再委託 |
| H26.3 | 鑑定評価の一括再委託 |
| H26.7 | 鑑定業務の一部再委託 |
| H27.10 | 鑑定業者でない業者からの再委託の可否 |
| H6.6 | 鑑定業者でない業者からの再委託の可否 |
署名押印等
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H26.7 | 鑑定業者の代表者の署名押印 |
| H26.8 | 自社鑑定士のみで行った鑑定評価書等の署名押印 |
| H27.2 | 鑑定評価書の署名押印箇所 |
| H28.7 | 鑑定評価書へ署名を刻印した「署名鑑」は自署にならない |
| H30.1 | 役割分担表の記載 |
| H30.5 | 派遣社員である不動産鑑定士の役割分担 |
| H30.10 | 電磁的記録による評価書交付の可否 |
| R3.5 | 電子署名の注意点 |
| R3.9 | 調査報告書の押印 |
| R3.9 | 電子ペンによる署名 |
| R4.1 | 複数名の電子署名 |
| R4.6 | 付属資料への電子署名 |
| R5.4 | 署名(財務諸表) |
| R5.4 | 署名(証券化対象不動産・財務諸表) |
価格等調査業務契約書作成に関する業務指針
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H26.1 | 依頼者が反社会的勢力であるか否かの本人確認 |
| H26.2 | 証券化対象不動産の受注資格要件 |
| H26.3 | 鑑定評価書の署名押印 |
| H26.7 | 業務提携時の契約書と依頼書兼承諾書標準モデル |
| H27.3 | 一人鑑定事務所の財務諸表作成に利用される案件の受託審査 |
| H28.1 | 官庁からの評価依頼時の確認書交付 |
| H28.10 | 契約書作成に関する基本指針 |
| H29.11 | 包括的な依頼書兼承諾書 |
| H30.5 | 経済価値の判定を伴う意見書を個人名で発行することの可否 |
| H30.7 | 印紙の必要性 |
| R2.3 | 自治体への確認書の交付 |
| R2.3 | 契約締結後の確認書の交付 |
| R2.9 | 依頼書兼承諾書の電子契約 |
| R2.9 | 標準委任約款の免責事項 |
| R3.4 | 確認書の交付と提出の違い |
| R3.4 | 複数件の依頼があった際の依頼書兼承諾書 |
| R4.4 | 電磁的記録による確認書 |
| R4.10 | 設立前の新法人宛の依頼書兼承諾書の運用 |
| R5.4 | 依頼書兼承諾書の保存義務 |
| R5.9 | 確認書(ガイドラインの適用範囲) |
| R5.10 | 確認書の発行日と記載事項 |
| R6.3 | 時点修正率等に係る業務の確認書交付 |
| R6.8 | 依頼書兼承諾書等の交付省略 |
不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H26.1 | 証券化財務諸表関連等評価の第三者受託審査 |
| H26.2 | 証券化鑑定評価における鑑定士の受託審査、報告審査の兼務 |
| H28.1 | インターネットからの受注及び成果物の電子媒体での発行 |
| H28.7 | 受任審査 |
| H28.12 | 業務実施態勢 |
| H29.1 | 不動産鑑定業者の業務提携 |
| H29.3 | 鑑定評価書の保存書類の範囲 |
| H29.4 | 不動産鑑定業者の業務提携 |
| H29.5 | 不動産鑑定業者の業務提携 |
| H29.8 | 業務実施体制 |
| H29.6 | 不動産鑑定士の専任 |
| H30.6 | 一人鑑定事務所の財務諸表作成に利用される案件の受任審査・報告書審査 |
| H30.10 | 非鑑定部署の鑑定士による受任審査・報告書審査 |
| R1.10 | 一人事務所の財務諸表のための価格調査 |
| R2.1 | 鑑定部門と仲介部門を兼務した際のリスク管理 |
| R3.6 | 報酬の発生しない業務 |
| R5.4 | 情報管理 |
| R5.5 | 情報管理 |
| R5.5 | 審査不動産鑑定士 |
| R5.6 | 未入会の鑑定士 |
| R7.3 | 情報管理(鑑定業者の「事務所」としての法的要件) |
その他
| 日時 | カテゴリ |
|---|---|
| H27.7 | 価格査定表(ドラフト)提出後の価格変更の可否 |
| H28.6 | 利回り等の提供は鑑定業法に反するか |
| H28.12 | 文書保管 |
| H29.1 | 複数の対象不動産を一冊の成果品として良いか |
| H29.3 | 鑑定評価書の審査 |
| H29.6 | 調査報告書の様式 |
| H29.10 | 価格等調査ガイドラインの適用範囲外の業務に係る依頼書等 |
| H29.12 | 公売時における鑑定評価の徴求 |
| H30.5 | 副本の署名押印 |
| H30.7 | 鑑定士の説明責任 |
| H30.12 | 依頼者以外への鑑定評価書の提出先等への提出方法 |
| H31.4 | 裁判鑑定の依頼 |
| R1.7 | 宅建業を兼業している際の価格査定書 |
| R1.11 | 裁判に係る自己のための意見書 |
| R1.12 | 電子署名付PDF |
| R2.2 | 鑑定評価業務の下請法の適用 |
| R3.12 | 割印の必要性 |
| R4.6 | 価格等調査ガイドラインの適用範囲 |
| R4.7 | PDF化後の紙の処分 |
| R4.12 | 価格の併記 |
| R5.4 | 反社会的勢力が居住する不動産の評価 |
| R5.7 | 利害関係 |
| R5.7 | 利害関係 |
| R5.11 | 評価書の保存 |
| R6.1 | 報告書審査チェックシートの使い方 |
| R6.1 | 価格等調査ガイドラインの適用範囲(私的鑑定のための成果報告書) |
| R6.2 | 報告書審査チェックシートの使い方 |
| R6.2 | 電子署名の差し替え対応 |
| R6.7 | 紹介料 |
| R6.8 | 他人鑑定評価書の時点修正 |
| R6.10 | 過去時点の鑑定評価 |
| R6.11 | 電子ファイルの提出方法等 |
| R6.12 | 依頼者以外(官庁)の情報公開請求 |
| R7.1 | 同一の評価書で複数類型の評価 |
| R7.1 | 限定価格での鑑定評価 |
| R7.1 | 財務諸表のための価格調査 |
記名不動産鑑定士の審査鑑定士兼務
 |
事例の取得を担当した、記名不動産鑑定士が報告書審査を担当することは可能ですか。 |
 |
本会が作成しております「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」にございますとおりです。 ~業務指針より(抜粋)~ |
業務提携における契約書面の必要性と例外
 |
「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」において、業務提携を行う場合には「業務提携を行う場合の不動産鑑定業者間の役割・責任分担を明確にする観点から、原則として業務提携に係る契約書面を取り交わすものとする。」とされていますが、この場合における「原則として」の例外として、どのような場合が想定されますでしょうか。依頼者が民間法人であっても契約書の取り交わしが必要となりますか。 |
 |
業務の受託においては契約当事者の誤解や紛争の発生を未然に防ぐためにも、契約書の取り交わしは重要となりますが、依頼者への説明責任及び守秘義務の観点からも、受託業者は、業務提携を行う場合にあらかじめ再委託先、再委託業務の範囲などの業務提携に係る契約内容等を明示して、依頼者の承諾を得る必要があります。また、業務提携を行う場合の不動産鑑定業者間の役割・責任分担を明確にする観点からも業務提携に係る契約書面を取り交わす行為は重要となります。 |
一人業者が一部再委託した場合の受託審査及び報告書審査(証券化以外)兼務
 |
不動産鑑定士が1名のみの事務所が鑑定評価(証券化対象不動産及び財務諸表の作成に利用される目的の鑑定評価を除く)の一部を提携業者に再委託した場合に、受託審査を担当した鑑定士が報告書審査を担当することは可能でしょうか。 |
 |
一人業者の場合、受付・受託審査・鑑定評価・報告書審査を一人で行うこととなりますが、鑑定補助方式の考え方では、鑑定評価の一部を提携業者に再委託したとしても、実質的に鑑定評価を行うのは、受託業者(一人業者)であると判断されます。 |
役割分担及び業務提携
 |
鑑定法第3条第2項業務を行う際に適用される業務指針、役割分担表記載例等はありますか。 |
 |
「不動産鑑定士の役割分担及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」の2適用範囲によれば、「本業務指針の適用範囲は、当分の間、鑑定評価業務を行う場合とするが、鑑定評価以外の業務(鑑定法第3条第2項の業務をいう)についても、可能な限り本業務指針を準用して適用することが望ましい。」 |
役割分担表の鑑定評価書への必要性
 |
①平成24年6月改正の「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」について |
 |
①国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会報告書「社会の変化に対応したよりよい鑑定評価に向けて」において、『Ⅱ 不動産の鑑定評価の質の向上に向けた取り組み/1.依頼者のニーズに応じた適正な業務提携の促進とその信頼性・透明性の向上/④鑑定士等の役割分担の明示』という項目があり、ここにおいて、“説明責任の実行等適正な鑑定評価業務の実施とその信頼性・透明性の向上のためには、鑑定業者間の役割分担のみではなく、鑑定評価における鑑定士の間の役割分担の明確化及び明示も重要である。(一部抜粋)”とされていることから、これを踏まえ、本会が作成する「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」において、“鑑定評価を行うに当たっては、依頼を受けた不動産鑑定業者が単独で業務を行うほか、他の不動産鑑定業者や専門家と提携して業務を行う場合があるので、鑑定評価書の作成に係わる者が、鑑定評価の核となる主たる部分に携わっているか否か、すなわち関与しているか否かにかかわらず、その役割分担を鑑定評価書に記載することは、信頼性・透明性の向上と不動産鑑定士の責任の所在を明らかにする観点から促進すべきと考えられる。”とし、“鑑定評価書における表示は、署名不動産鑑定士については冒頭に署名押印することとし、記名不動産鑑定士及び他の専門家については、末尾に記載する役割分担表に明示することとする。(いずれも[3 不動産鑑定士の役割分担と署名義務]より抜粋)”とし、役割分担表の記載を義務付けております。 |
業務提携のひな型文書
 |
他県の物件について、自身が統括鑑定士となり、物件の確認、事例収集を現地の鑑定士に依頼する場合の留意事項、提携文書のひな形があれば教えてください。 |
 |
本会において、「提携文書のひな型」は、作成しておりません。 |
不動産鑑定士1名事務所の役割分担表
 |
証券化対象不動産及び財務諸表の作成に利用される目的の鑑定評価以外の鑑定評価基準に則った鑑定評価書で不動産鑑定士が1人しかいない場合、報告書審査・受託審査を署名不動産鑑定士が行うことができると指針に規定されていますが、この場合でも役割分担表の記載が必要でしょうか。 |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の5(3)及び7(3)の「この場合」以下のとおり、役割分担表への記載が必要であり、具体的な記載が必要です。具体的な記載方法は、「不動産鑑定士の役割分担表及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」の「別紙3」を参考としてください。 |
提携業者の鑑定評価書の保管義務業者
 |
業務提携で鑑定評価を行った際の書類の保管義務について質問です。 Aという業者に甲という統括鑑定士がいて当社Bの業者に乙という統括鑑定士以外の署名鑑定士がいる場合、Aの顧客の依頼によりAと当社Bの業務提携により行った鑑定評価について、Aという業者の記名押印、統括鑑定士甲と乙の署名のある鑑定評価書を顧客に提出した際に、 1.当社Bは、不動産の鑑定評価に関する法律にもとづいて、鑑定評価書の写しを保管する義務はありますか? |
 |
ご照会の場合については、法令を読む限り、保管義務はA社のみとなり、B社に対してはありません。鑑定評価基準においても保管義務についての記載はありません。 保管すべき期間は、規則により5年とされます。 ■不動産鑑定法第39条 |
事例収集の業務提携及び評価書の保管
 |
事例の収集の件ー業務提携で行ってよい場合の判断として。 |
 |
事例収集を業務提携で行った場合には、履歴管理表は取得した鑑定士が関わります。当然のこととして、関与した鑑定士として本人の名前が記名されるのでしょうから、ご質問者の意見のように事後の問い合わせ等に対応できるようにしておくべきだと思います。 国は、法令上は保管義務はない、としていますが、法令違反であるか否かのこととは別に鑑定評価に関与した鑑定士としての責任があります。後日の無用な紛争を予防する意味でも鑑定書の写しを保管する方が望ましい、と考えます。 次に、取引事例の扱いとして、共同利用が適切に行われていることを説明する義務もあります。 したがって、該当部分のみを保管するのでは用をなさない、と言えます。 |
報告書の審査と署名不動産鑑定士の役割分担
 |
不動産鑑定士の役割分担についての質問です。 |
 |
報告書審査については、鑑定評価に関与した不動産鑑定士(統括不動産鑑定士を含む署名不動産鑑定士)から独立した立場で行う必要があり、 |
総括不動産鑑定士が確定担当鑑定士の場合の実査
 |
不動産鑑定士の役割分担についての質問です。 |
 |
価格等調査ガイドラインによれば、契約の締結までに業務の目的と範囲等を確定し確認書を依頼者に交付するものとし、その後変更する場合には、変更内容を確定し、成果報告署の交付までに、変更後の確認書を交付するものとされています。 |
不動産鑑定評価報告書のレビュー
 |
他の不動産鑑定業者から不動産鑑定評価報告書のレビュー(独立した立場でその内容チェック、再検討項目の指摘等)業務を受託するにあたり以下ご質問があります。 |
 |
①ご判断のとおりと考えます。 ②ご判断のとおりと考えます。 ③新型コロナウィルス感染症への対応の一環として、会員専用ページにてひな形を公開しておりますのでご参考にしてください。 |
役割分担表の省略
 |
担保評価の参考とすることを依頼目的とする、「基準に則らない成果報告書」についてお尋ねします。 |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」では、鑑定評価における役割分担と責任の所在を明確にし、不動産鑑定士に対して役割に対する責任の自覚を促すため、鑑定評価書(鑑定法第3条第1項の鑑定評価業務の成果として交付されるもの)の末尾に役割分担表を添付することとしています。 |
役割分担(財務諸表)
 |
当事務所は一人の常勤鑑定士(私)に非常勤の鑑定士(1人・契約)がいます。 |
 |
下記のとおり役割分担して対応することが考えられます。 |
業務提携(REA-Jirei)
 |
業務提携に係る契約書面と、新しいREA-Jireiの依頼者選択の関係についてお尋ねします。 |
 |
業務提携契約につきましては、原依頼者の承諾を得たうえで、元請けと下請けの間で締結します。 |
署名不動産鑑定士の審査鑑定士兼務
 |
ご質問1 |
 |
ご質問1 |
個人鑑定士の審査鑑定士兼務
 |
報告書審査を他の不動産鑑定士に依頼しようと考えていますが、依頼予定鑑定士は近く自らの鑑定事務所の閉鎖を予定しております。しかし、不動産鑑定士として登録は存続し、協会(本会及び府士協会)にも引き続き所属する予定です。鑑定業者に所属していない個人鑑定士を報告書審査鑑定士として役割分担することは可能でしょうか。 |
 |
鑑定評価報告書の審査については、不動産鑑定業者に所属していない不動産鑑定士が行っても特段差し支えないと考えます。 |
鑑定業務の一括再委託
 |
受託した鑑定評価業務を一括して再委託し、自身で内容を精査したうえで署名押印を行い鑑定評価書として完成させることに問題はありますか。 |
 |
本会が作成している不動産鑑定評価制度改正に関する指針等における「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」に記載されておりますが、【6 一括再委託の制限】において「鑑定評価を行う場合に、受託業者に所属する不動産鑑定士は、総括不動産鑑定士又は総括不動産鑑定士以外の署名不動産鑑定士として鑑定評価に関与し、鑑定評価書に署名押印することとなるため、依頼内容の全部を一括して他の不動産鑑定業者に委託すること(一括再委託)は、事実上制限されることとなる。」とあります。 |
鑑定評価の一括再委託
 |
A鑑定業者がB鑑定業者に鑑定評価の全段階を委託し、鑑定評価書の発行はA鑑定業者で行う業務提携行った場合、以下のように業務を分担し、評価書に署名押印及び記名することは可能ですか。 |
 |
本会が作成している不動産鑑定評価制度改正に関する指針等における「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」に記載されておりますが、【6 一括再委託の制限】において「鑑定評価を行う場合に、受託業者に所属する不動産鑑定士は、総括不動産鑑定士又は総括不動産鑑定士以外の署名不動産鑑定士として鑑定評価に関与し、鑑定評価書に署名押印することとなるため、依頼内容の全部を一括して他の不動産鑑定業者に委託すること(一括再委託)は、事実上制限されることとなる。」とあります。 |
鑑定業務の一部再委託
 |
依頼者から鑑定評価の依頼を受けた受託鑑定業者が、他の鑑定業者の代表者である不動産鑑定士に対し、業務提携契約を締結のうえで、鑑定業務の一部を委託することは認められますか。 |
 |
「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」に記載されているとおりです。一括再委託に関しては制限をされておりますが、一部委託に関しては問題がないと考えられます。 なお、業務提携は業者間での契約を前提に、各業者間の業務範囲及び各業者内における不動産鑑定士の役割分担・責任範囲を明確にするものです。 また、依頼者が公共・民間どちらか分かりませんが、委託契約書等において、依頼者が承諾した場合を除き、再委託を制限する等の規定がありますのでご留意ください。 |
鑑定業者でない業者からの再委託の可否
 |
不動産鑑定評価業務を含む調査業務の受託業者(鑑定業者ではないA社)が業務を委託し、鑑定業者であるB社へ不動産鑑定評価業務を再委託することへの可否 |
 |
Aが依頼先Cから包括的調査業務を受託し、調査事項の内鑑定評価業務を鑑定業者Bに発注する場合であれば、鑑定評価の依頼者はA、鑑定評価書の宛先もA、評価書の提出先としてCとなることが想定できる。この場合であれば、再委託とは言えず、業務提携でもないことから業務指針の適用にはあたらない、と考えられます。 |
鑑定業者でない業者からの再委託の可否
 |
取引先から企業買収にかかる「包括的調査業務」を受託するケースを想定しております。また企業買収にかかる調査項目の一つに「不動産価格」の算定があり、この部分については不動産鑑定業者に再委託を行い、当方の資料に情報ソースを明らかにした上で掲載することを想定しております。 |
 |
不動産鑑定業務について、再委任を行うことを一律禁止した規程等はございません。 |
鑑定業者の代表者の署名押印
 |
鑑定業者の代表取締役社長など、鑑定評価の受託・発行を管理する立場にある鑑定士が、鑑定評価の主たる部分に関与していない場合にあっても記名不動産鑑定士としての責任より重い責任を負うべく、評価書に署名押印を行うことに問題はありますか。 |
 |
不動産鑑定評価書の発行にあたっては、“鑑定業者としての責任”と、“不動産鑑定士としての責任”が発生します。 |
自社鑑定士のみで行った鑑定評価書等の署名押印
 |
複数の物件を対象とした「連結決算・連結納税のための時価評価」を依頼目的とした価格調査(鑑定評価基準に則らない価格調査)を受託した際、業務提携を行わず、全案件の評価を自社鑑定士で行う場合であっても調査報告書の表紙に総括不動産鑑定士及び実際に査定を行った鑑定士の併記が必要となりますか。 |
 |
本会が作成しております「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」『5 署名不動産鑑定士、記名不動産鑑定士が担当する業務(2)総括不動産鑑定士が担当する業務』に記載されておりますとおり、“なお、業務提携を行わなくとも、同一不動産鑑定業者において関与する不動産鑑定士が複数の場合には、実態に即して同様の扱いとするが、担当した署名不動産鑑定士の一人が、依頼者又は利用者に対応できる場合は、必ずしも総括不動産鑑定士を置く必要はない。総括不動産鑑定士を置いた場合は、その位置づけや役割について依頼者又は利用者に誤解を与えないよう、鑑定評価書の役割分担表にその業務内容を記載することが必要となる。”としておりますので、総括不動産鑑定士を置いた場合は、役割分担表へ記載する必要があります。また、総括不動産鑑定士は、関与不動産鑑定士として、署名押印が必要です。 |
鑑定評価書の署名押印箇所
 |
鑑定評価書への署名押印を評価額の記載があるページ別の箇所にすることは可能ですか。 |
 |
署名押印箇所について、「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」に記載の通り、署名不動産鑑定士については鑑定評価書冒頭への署名押印義務を規定しておりますが、特に鑑定評価額記載ページ内への署名押印を義務付けてはおりません。 |
鑑定評価書へ署名を刻印した「署名鑑」は自署にならない
 |
鑑定評価書の署名の件ですが、評価書へは自分の署名を刻印した「署名鑑」を押印しているのですが、これでよろしいのでしょうか。 |
 |
鑑定評価書に対する署名押印とは、不動産鑑定評価法第39条2項に定められる法律上の規定であり、通常、自署による氏名の記入及び押印であると考えられます。 |
役割分担表の記載
 |
鑑定評価に記載する「役割分担表」について、総括不動産鑑定士Aとその他の不動産鑑定士Bの2名いる場合で、総括不動産鑑定士Aがメインで評価を行い、その他の鑑定士Bが事例取得と審査のみ行う場合の記載方法を教えてください。 |
 |
総括鑑定士とは、「依頼者に提出する鑑定評価書について、作成に関わる複数の不動産鑑定士を指導するとともに、鑑定評価の結果を検証することを主たる業務とする。所謂コーディネーター的な位置づけとして鑑定評価に関与し、担当した署名不動産鑑定士と共同して責任を負うものであるが、対外的には一時的かつ総括的な説明責任を有することになる。総括鑑定士は、業務受任の形態に応じて任意に設置可能であるが、少なくとも署名不動産鑑定士を指揮するとともに鑑定評価の結果を検証する役割を担うものである。」とされています。 お問い合わせのケースでは、総括鑑定士Aがほぼ業務全般を担当しているので、(Bの鑑定評価への関わり方が低ければ、署名鑑定士Aのみで良い場合もありますが)署名鑑定士2名とするとしても1名「総括」鑑定士の設置は任意のケースとも考えられます。 また、ご質問者の判断では、受任審査がA・B両方に記載されていますが、例えばAが受任し、受任審査をBが行う(あるいはその逆)とすべきです(=業務の受任はどちらか一方で行い、もう一方がその適否を審査する)。 また、A・Bそれぞれが行った業務の役割分担の内容についての具体的記載内容や、報告書審査の内訳などの記載例については、「不動産鑑定士の役割分担等および不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針P11(別紙4)」を参考にしてください。 |
派遣社員である不動産鑑定士の役割分担
 |
「署名不動産鑑定士」について質問します。 当社では、現在正社員である不動産鑑定士が署名不動産鑑定士となっていますが、仮に派遣契約で不動産鑑定士を採用した場合、その派遣社員が署名不動産鑑定士として活動することに問題はありますか? |
 |
不動産鑑定士として鑑定業者の業務に従事する場合には、その鑑定業者の名称や従事する事務所名称などを登録する必要があります。
また、他の鑑定業者の事務所に移動した場合、または同じ鑑定業者内で他の事務所に移動した場合には、変更の登録申請が必要になります。 |
電磁的記録による評価書交付の可否
 |
鑑定評価書及び調査報告書の本紙提出の必要性について、ご質問させていただきます。 |
 |
①本会では過去に下記回答を行っておりますので、ご確認下さい。 |
電子署名の注意点
 |
不動産鑑定評価書の電子署名化を検討しております。 |
 |
不動産鑑定評価書の電子化に関するQ&Aをご参照ください。 |
調査報告書の押印
 |
令和3年9月1日以降、不動産鑑定評価書における鑑定士の押印が廃止されますが、不動産調査報告書に関しても、押印を廃止しても有効という認識でよろしいのでしょうか。また、鑑定評価書及び不動産調査報告書における鑑定業者の押印(代表者印)が無くても、当該鑑定評価書等は有効という解釈でよろしいのでしょうか。 |
 |
名称の如何にかかわらず「不動産の経済価値を価額に表示」する行為であれば鑑定評価であり、従来であれば署名押印義務、改正後は署名のみで対応可能と考えます。 |
電子ペンによる署名
 |
国不地第13号 鑑定評価書の押印廃止について(通知) |
 |
①鑑定法では、鑑定業者の押印については特に規程はございませんので、押印する義務はありません。押印の必要性については、依頼者や開示・提出先等との関係をふまえて、各鑑定業者でご判断下さい。 |
複数名の電子署名
 |
鑑定評価書への電子署名について、以下の①②の通り、複数名の電子署名がなされていても問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。 |
 |
関与不動産鑑定士全員の電子署名がなされていれば、鑑定法第39条第2項に抵触することはないと考えます。 |
付属資料への電子署名
 |
鑑定評価書の電子化について、附属資料についても電子署名証明の付与が必要でしょうか。 |
 |
不動産の鑑定評価に関する法律では、「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。」とされております。 |
署名(財務諸表)
 |
財務諸表のための鑑定評価について、以下の点ご教授ください。 |
 |
受任審査・報告書審査を行うだけであれば、報告書への署名は必要ございません。 |
署名(証券化対象不動産・財務諸表)
 |
証券化対象不動産及び財務諸表の作成に利用される目的の鑑定評価にあたっての質問です。 |
 |
受任審査・報告書審査を行うだけであれば、報告書への署名は必要ございません。 |
依頼者が反社会的勢力であるか否かの本人確認
 |
価格等調査業務約款について、価格等調査業務依頼書兼承諾書とともに添付する依頼約款に反社会的勢力の排除の条項が記載されていますが、依頼者の本人確認義務とその方法をご教示ください。また、「価格等調査業務依頼書兼承諾書」により依頼者と契約を取り交わす際の本人確認方法を教えてください。 |
 |
依頼者が本人であるか否かを確認する義務までは求められていないものと判断します。通常は約款(反社会的勢力排除条項)を提示して確認し、依頼者が本人以外の者と判明した段階で契約解除する等の対応になるかと思います。 |
証券化対象不動産の受注資格要件
 |
証券化対象不動産の評価を受注するのに必要な鑑定業者の要件はありますか。 |
 |
鑑定業者にかかる「義務的な資格要件」はございません。 |
鑑定評価書の署名押印
 |
鑑定評価書の署名押印について、鑑定評価を行った部門長、もしくは会社代表の押印は必要となりますか。 |
 |
鑑定評価書における“鑑定業者の押印”は義務ではないことから、会社代表者の押印でなくても特に問題はありませんが、少なくとも業者の責任者としての担当部署の長の押印があるほうが望ましいものと考えます。 |
業務提携時の契約書と依頼書兼承諾書標準モデル
 |
本会作成の依頼書兼承諾書標準モデルを業務提携の際に提携先との契約書として利用してもよろしいですか。また、業務提携は案件ごとに個別に契約を結ぶ形で問題はありませんか。 |
 |
価格等調査業務依頼書及び承諾書の標準モデルは、依頼者との契約を前提としていることから業務提携契約書にそのまま使用できるとは思えませんが、業務提携契約書の記載事項は、価格等調査業務依頼書及び承諾書の依頼内容を参考として、委託業務の範囲に応じて適切に定める必要があります。(役割・責任分担の明確化) |
一人鑑定事務所の財務諸表作成に利用される案件の受託審査
 |
財務諸表の作成に利用される目的での鑑定評価に関し、報告書審査は業務提携で行うことができても、受託審査は受託業者の責任で行うべきとのことであり、「財務諸表のための価格調査に関する実務指針」7-3受託審査についてでは、「必ず、受付担当者以外の不動産鑑定士が審査しなければならず」との記載があります。 |
 |
所属不動産鑑定士が一名の事務所において、当該不動産鑑定士を受付担当者として証券化対象不動産または財務諸表作成に利用される目的の案件を受託する際は、縦分業型業務提携を行った上で、受付担当者以外の不動産鑑定士が受託審査を行う方法が考えられます。 |
官庁からの評価依頼時の確認書交付
 |
「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」につきお尋ね致します。 |
 |
価格等調査ガイドラインでは、次のように規定しています。契約の締結までに、以下の事項を依頼者に確認したうえで確定するものとする。不動産鑑定業者は、以下の事項を明記した文書等を契約の締結までに依頼者に交付するものとする。 |
契約書作成に関する基本指針
 |
市からの調査業務委任で、総合建設コンサルタントが受任し、鑑定業者が資産評価の部分を下請した場合について、建設コンサルタントから指定された鑑定評価の契約書式で受任しても問題ないでしょうか。 |
 |
契約書自体はガイドライン等で明記しておらず、契約書の書式をどのようなものとするかは、当事者の自由と言えます。 |
包括的な依頼書兼承諾書
 |
依頼書兼承諾書について、年間に大量にもらうクライアントの場合について 案件都度ではなく、包括的な依頼書兼承諾書を年1回結び、個別の内容を確認書にて確認いただく方式は可能でしょうか? |
 |
現行「価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針」によると、P3「7 契約書に記載すべき事項」において、「…継続的な取引関係にある依頼者との間においては、上記の内容(契約書に記載すべき事項)のうち、共通事項を基本契約として定め、案件ごとの個別事項を個別契約として定める方法も考えられる」とされています(したがって、基本契約書があれば、案件ごとの個別契約の記載内容を簡略化することは可)。 |
経済価値の判定を伴う意見書を個人名で発行することの可否
 |
経済価値の判定を伴う不動産意見書は、鑑定法上は鑑定評価に該当すると考えられますが、個人名での発行は出来ますか。 不動産鑑定業者に所属する不動産鑑定士ですが、報酬を会社ではなく個人で受領したいと考えています。 |
 |
ご指摘の通り、お問い合わせの「経済価値の判定を伴う不動産意見書」は、価格等調査ガイドラインの適用範囲である「鑑定法第3条1項の業務」に該当し、同時に不動産の鑑定評価に関する法律の適用範囲にもなります。 同法には、「不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない(33条)」とされており、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うためには、業者登録が必要」とされています。 したがって、本件お問い合わせにあるような業務を個人で受任し、「個人名で発行する」ためには、前提として、個人名での業者登録が必要です。 また、報酬の受け取り方に関しては、所属業者との協議事項であり、ガイドラインや鑑定法の適用の有無とは別の問題になると考えます。 |
印紙の必要性
 |
固定資産税の適正な評価を行うため、不動産鑑定士に標準宅地の鑑定評価及び時点修正を行っていただいている。 『価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針』の「5 価格等調査業務の契約に係る法的解釈」において、「不動産の鑑定評価契約は委任契約に該当することから請負に関する契約書(第2号文書)その他いずれの課税物件にも該当しないため印紙税の課税義務はない。」との記載があるが、不動産の鑑定評価委託契約はすべて、有償委任契約と解して、契約書への印紙の貼付は不要と考えてよろしいか。 |
 |
価格等調査業務に係る契約書面の印紙税の取り扱いにつきましては、以前本会から東京国税局に照会を行い、下記のとおり回答をいただいております。 |
自治体への確認書の交付
 |
東京都(建設局)の請書や、市の契約書に、「『・・・カイドライン』に基づく『・・・確認書』及び『・・・依頼書兼承諾書』については本請書(又は依頼書)をもって代えるものとする」という文章があります。 契約書等に上記の文言がある場合でも確認書を交付しなければならないでしょうか。 |
 |
国土交通省の見解によれば、地価公示等別途法令で定める業務以外は確認書の交付が必要とされています。 |
契約締結後の確認書の交付
 |
業務の目的と範囲等の確定に係る確認書には「契約の締結までに交付するものです。」と記載されているが、対象不動産の確認後とすることはできないかお教えください。 官庁との契約は依頼書の発行と、承諾書引渡で契約成立となるが、事務処理上当日や翌日までの提出を求められる場合がある。調査範囲等条件については、対象不動産を確認しなければ、条件設定の適否を判断できないので、確認書の提出を契約締結から対象不動産確認後速やかにと変更できなでしょうか。 |
 |
国土交通省が定める「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」では、不動産鑑定業者は契約の締結までに確認書を依頼者に提示することが求められております。 |
依頼書兼承諾書の電子契約
 |
「価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針」を拝見しました。 |
 |
価格等調査業務依頼書兼承諾書は契約書です。したがって、依頼者と協議のうえ、各自法令に沿ってご判断ください。 |
標準委任約款の免責事項
 |
2020.3に改正として提示されました価格等調査業務標準委任約款について、質問です。 |
 |
第5条(1)について |
確認書の交付と提出の違い
 |
「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」の2依頼目的、利用者の範囲等、⑤鑑定評価書の提出の有無について、依頼者に対しては不動産鑑定評価書「交付」と理解しております。「提出」と使い分けている意味をご教示ください。 |
 |
交付は鑑定業者が行う行為で言葉使いも含め法律で定められています。 |
複数件の依頼があった際の依頼書兼承諾書
 |
「価格等調査業務依頼書兼承諾書(以下「承諾書等」と称す)について |
 |
1.複数件(ex.10件)の依頼があった場合、その都度承諾書等(契約約款も含む)を作成・提示するものでしょうか。 |
電磁的記録による確認書
 |
「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」(以下、「確認書」についてのご質問です。 |
 |
価格等調査ガイドラインにおける、確認書に関する記載は下記のとおりです。 |
設立前の新法人宛の依頼書兼承諾書の運用
 |
依頼者兼承諾書について、お聞きします。 |
 |
まず個人の方と契約して契約書の取り交し・確認書の交付を行い、法人設立時点で契約を変更したうえで、再度確認書を会社あてに交付することでよろしいかと思われます。 |
依頼書兼承諾書の保存義務
 |
依頼書兼承諾書や公的評価契約書(主に国税)は5年間の保存義務はあるのでしょうか? |
 |
鑑定法では、①鑑定評価書の写し、②対象不動産等を明示するに足りる図面、③写真、④その他資料について保存義務がございます。 |
確認書(ガイドラインの適用範囲)
 |
現在行っている鑑定評価業務は確認書の交付が必要なのか調べております。 |
 |
ご照会いただいた業務の内容は、公共用地買収のための不動産鑑定業務であると思われます。 |
確認書の発行日と記載事項
 |
1.確認書の発行日(交付日) |
 |
1.確認書の発行日(交付日) |
時点修正率等に係る業務の確認書交付
 |
時点修正率や格差率の意見書の場合、業務の目的と範囲等の確定に係る確認書の交付は必要か。 |
 |
時点修正等に係る業務内容が「価格等調査」に該当する場合は、確認書の交付が必要です。
「価格等調査」とは、不動産の価格等を文書等に表示する調査を言います。 |
依頼書兼承諾書等の交付省略
 |
依頼者と包括業務委託契約にて業務を受注することを考えている。予定している包括業務委託契約書を取り交わすことにより、受注の度に交付している、確認書や業務依頼兼承諾書などの交付を省略したいと考えている。あらかじめ業務の内容や報酬額について、包括業務委託契約書に記載すれば、案件の受注の度に確認書や依頼書兼承諾を交付する必要はないのか。 |
 |
ご質問の件に関しましては、下記のとおりと考えられます。 |
証券化財務諸表関連等評価の第三者受託審査
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の改正に関して、証券化対象不動産及び財務諸表の作成に利用される目的の鑑定評価については、従来通り第三者による受託審査が必要となりますか。また、総括不動産鑑定士による審査は可能ですか。 |
 |
財務諸表関連及び証券化に関する受託審査・報告書審査は、H24.6の「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の改正前後で、取扱いに変更はございません。 |
証券化鑑定評価における鑑定士の受託審査、報告審査の兼務
 |
証券化対象不動産の鑑定評価について、不動産鑑定士が2名の事務所が業務を行う場合、受託審査担当鑑定士が報告審査担当鑑定士を兼ねることは問題ないのでしょうか。 |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」上、「受託審査鑑定士と報告書審査鑑定士が同一人」であることを否定するものではありません。 |
インターネットからの受注及び成果物の電子媒体での発行
 |
「鑑定評価書」及び「調査報告書」の受注にあたり、インターネット上のサイトから依頼を受けることについては問題ございませんでしょうか? |
 |
ウェブサイトを経由した鑑定依頼の申込を受けることは可能でしょうが、鑑定評価が委任業務であることを考えると、契約の申込段階に当たり、鑑定業者は申込を受けた業務について、依頼者と対面ではなくとも電話等の手段をとり内容を確認する必要があります。 |
受任審査
 |
鑑定評価(各論3章証券化対象不動産、財務諸表関連)及び調査報告書(各論3章証券化対象不動産、財務諸表関連)以外の依頼目的による鑑定評価や調査報告書について、「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の別紙2受託審査項目のチェックに基づく受託の適否判定を行う必要はありますか。 |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」(平成27年3月17日一部改正)の適用範囲については、 「2 適用範囲及び用語の定義」において、以下のように定められています。 |
業務実施態勢
 |
2名の不動産鑑定士が在籍しているが、うち1名が療養のため、業務を行うことができなくなった場合、1名が復帰するまでの間、「自己による報告書審査の特例」を準用することは可能ですか? |
 |
お問い合わせの場合には、所属鑑定士が一人となって1人鑑定業者になったことと言えます。専任鑑定士の変更と違い、所属鑑定士の異動は届出事項となっておりません。対外的に所属鑑定士が複数であることを明示していない場合に限り、社内審査は1人鑑定業者と同様に行ってかまわない、と考えられます。 |
不動産鑑定業者の業務提携
 |
提携業者(要押印部分担当)により鑑定評価を行った場合、受託業者が発行した最終鑑定評価書の成果品(印影の写しがあるもの)の控え(紙ベースまたはPDF及びワードやエクセルなど)を提携業者が保管する義務はないのでしょうか?
あくまで、提携業者と受託業者との契約関係で決まるものでしょうか。 |
 |
提携業者に対し、国は、法令上は保管義務はない、としていますが、法令違反であるか否かのこととは別に鑑定評価に関与した鑑定士としての責任があります。後日の無用な紛争を予防する意味でも鑑定書の写しを保管する方が望ましい、と考えます。ご質問者の意見のように事後の問い合わせ等に対応できるよう、全体の控えをとっておくべきだと思います。 |
鑑定評価書の保存書類の範囲
 |
不動産の鑑定評価に関する法律 第三章第三十九条3「不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。」の内容について |
 |
1. 保存種類の範囲について |
不動産鑑定業者の業務提携
 |
不動産鑑定士が1名の事務所において、証券化対象不動産若しく財務諸表作成に利用される目的の価格等調査業務又は不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価業務を行う場合、外部の不動産鑑定業者に審査を委託する必要があるのでしょうか。 |
 |
不動産鑑定士が1名のみの事務所における受託審査、報告書審査については、業務の内容により以下のとおり対応することとなります。 |
不動産鑑定業者の業務提携
 |
鑑定評価にあたっての役割分担表について、どこまで作業を外部にお願いした場合に記載義務があるのか、教えてください。 |
 |
鑑定評価書に役割分担表を添付する目的は、「責任の所在を明確にすること」です。したがって、たとえ外部専門家による報告書内容を記載するとしても、そこに記されたことを取捨選択するのは担当不動産鑑定士であって、そのことが鑑定評価に反映された結果は担当不動産鑑定士が追うべきものであり、外部の専門家が負うべきものではありません。さらに、鑑定評価の各段階において事実に対する判断が行われます。 言い換えれば、鑑定評価は判断業務であり、不動産鑑定士資格を有する者にしか出来ません。しかし、全ての業務を鑑定士が行うことまで求められているわけではなく、補助者に業務の一部を担当させ、最終的に不動産鑑定士が内容を確認することは許されています。また、下調べしたデータを資料として見やすく作成することを社内、あるいは社外の担当者に委ねることもあり得ます。 同様に、外部の専門家に資料を作成してもらい、評価書の一部とすることも考えられます。 |
業務実施体制
 |
監査法人が監査を行ううえで、企業より提示された鑑定評価書の内容をレビューし、問題がないかを確認して欲しいという依頼を受けております。企業より提出された鑑定評価書の依頼目的が、「財務諸表作成のため」でなく、受託審査等を1名の鑑定士が行われている鑑定評価書が提示された場合、どのような対応をするのが良いでしょうか? |
 |
「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方」 |
不動産鑑定士の専任
 |
A社の専任不動産鑑定士として鑑定業を行いつつ、同業者のB社で非専任として鑑定業務等に従事することは、鑑定業法上可能でしょうか。 |
 |
本会会員に対し、本会通知「鑑111号(平成27年10月9日付)専任鑑定士の役割について」にて、国土交通省から「鑑定業者の専任鑑定士に該当する者が、恒常的に他の鑑定業者の業務と掛け持ちで当該他業者の鑑定評価書を作成しているケース等、不動産鑑定士の登録内容に疑義がある例があった。」旨の指摘を受けたことが周知されています。 |
一人鑑定事務所の財務諸表作成に利用される案件の受任審査・報告書審査
 |
一人鑑定士事務所では、「財務諸表作成に利用される目的」の案件は、「縦分業型業務提携」を行わなければ、受任できないことになるのでしょうか? |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」は、次の価格等調査業務を行う場合に適用します。 |
非鑑定部署の鑑定士による受任審査・報告書審査
 |
受任審査と報告書審査についての質問です。
鑑定士が複数所属の法人事務所で、鑑定法第3条第1項業務のみを行う部署と第1項業務以外の業務(例えば固定資産路線価評価業務や鑑定評価研究など)のみを行う部署に分かれている場合、第1項業務のみを行う部署に所属する鑑定士が1名のときには、その他の部署の鑑定士が受任審査や報告書審査業務を必ず担当しなければいけないのでしょうか。 |
 |
現行の業務指針では、①不動産鑑定業者として行うことが適切な業務であるかを審査する受任審査は、受付担当者(不動産鑑定士とは限らない)以外の不動産鑑定士1名以上が担当すること(不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針P3(3)参照)、②個々の業務における成果報告書の質を維持・向上させるために行う報告書審査は、署名不動産鑑定士以外の不動産鑑定士1名以上が担当することと、とされており、不動産鑑定業者として、業務及び成果報告書の質の維持・向上に最大限努めることを定めています。 |
一人事務所の財務諸表のための価格調査
 |
財務諸表のための価格調査について、不動産鑑定士が1名の場合に、不動産鑑定業者が業務提携等を行うことなしに、行うことができるのでしょうか。 |
 |
鑑定評価の結果が依頼者以外の広範囲の者に影響を及ぼすこととなる証券化対象不動産の鑑定評価又は財務諸表の作成若しくは企業会計に関連した鑑定評価については、通常の依頼目的以上に透明性・信頼性向上を目指す必要があることから、各種業務指針等を策定した経緯があります。 |
鑑定部門と仲介部門を兼務した際のリスク管理
 |
・鑑定部門の職員(不動産鑑定士=専任以外)を、仲介営業部門の職員と兼務させることを検討しております。 |
 |
ご認識のとおり、リスク管理態勢をしっかり取っていただく必要があります。 |
報酬の発生しない業務
 |
弊社鑑定部署では、業務領域の拡大として「報酬の発生しないCRE等各種提案」業務(提案書作成~プレゼンテーションまで)への取組を予定しています。 |
 |
法第二条の業にあたらない業務であっても、不動産鑑定士が特定の不動産の価格等を表示する行為は問題となる可能性があり、不動産鑑定士の信頼性を基礎とする広告・提案などにおいても、利用者等に誤解を与えることのないよう充分な配慮が必要と考えます。 |
情報管理
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する実務指針」内の8.情報管理(2)「鑑定部門における他業種部門との独立性を維持するために、物理的区画・情報アクセス管理等の必要な態勢等を講じる」と記載されていますが、これはネットワーク内に他部門がアクセスできない独立したフォルダを作成し、管理するという運用で問題ないでしょうか。それとも、スタンドアロンPCにより運用する必要があるのでしょうか。 |
 |
管理する情報の機密性によって御社でのルールに従い管理する必要があります。 |
情報管理
 |
現在、宅建業と鑑定業が兼業しておりますが、部門間で、物理的区画・情報管理等を適切に組織構築してあります。 |
 |
不動産の鑑定評価に関する法律等(以下「鑑定法」という。)の規定では、鑑定業者が自らのために鑑定評価を行うことを特段禁止しておりませんが、鑑定法の解釈に係る事項ですので、詳細は国土交通省にお問い合わせください。 |
審査不動産鑑定士
 |
「専任不動産鑑定士」が、「受任審査者」及び「審査不動産鑑定士」とならなければならないという規定はございますでしょうか。 |
 |
専任不動産鑑定士でない不動産鑑定士でも、受任審査・報告書審査を行うことは可能です。 |
未入会の鑑定士
 |
弊社の鑑定評価書には、「公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会」「不動産鑑定業者 〇〇株式会社」と明記し、連合会に所属する不動産鑑定士が署名しております。 |
 |
「公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 業者会員」等記載していただき、依頼者から誤認されないようご対応ください。 |
情報管理(鑑定業者の「事務所」としての法的要件)
 |
(前提) |
 |
・鑑定士・業者には鑑定法第6条・第38条で守秘義務が課されておりますので、当該規定を遵守するために必要な対応を行うべきと考えられます。 |
価格査定表(ドラフト)提出後の価格変更の可否
 |
「不動産鑑定業者の業務態勢に関する業務指針」の内示におけるドラフトの定義に関してです。
「不動産鑑定業者の業務態勢に関する業務指針」6 価格等調査業務の実施(6)に、以下の記載があります。 |
 |
「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」6価格等調査業務の実施の(6)において、「その形式に関わらず依頼者に価格等を示す行為は、不動産鑑定士として価格等の判断を示すことである」とされており、価格査定表(別紙)のみの提出であっても価格等を示す行為であれば、原則として価格等の変更を行ってはならないと解されます。「ただし、ドラフト提出後に、価格等調査の前提条件、資料の変更・解釈その他合理的な理由によって価格等を変更することとなった場合は、不動産鑑定業者内であらかじめ定められた手続き等に従って対応するものとする。この場合において、価格等の変更に至った合理的な理由について文書等に記録するなど、後日依頼者その他に説明が可能な状態にするものとする。」とされています。 |
利回り等の提供は鑑定業法に反するか
 |
鑑定士でない者が下記を行うに当たって、鑑定法に反するか否かを教えてください。 【ご質問者の判断】 |
 |
不動産の鑑定評価に関する法律 第二条には次のように記載されています。 |
文書保管
 |
本会文書 平成25年11月1日付の鑑119号「鑑定評価書の保存について」1.法第29条第2項の規定に関連して |
 |
「国土交通省の所管する法令にかかる民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」第3条および別表第1により、鑑定評価書の写しその他の書類の保存は電磁的記録により行うことができるとされております。 |
複数の対象不動産を一冊の成果品として良いか
 |
依頼者に対して、複数不動産(全国各地に散らばってます)をそれぞれ価格を明記するものの、1冊の成果品として提出することは可能でしょうか。 |
 |
評価作業は、次のような各段階を踏まえて進められます。 |
鑑定評価書の審査について
 |
鑑定士に評価して頂いた額が適正かどうか、審査をして頂けるような何らかの機関を紹介して頂けますか。 また、何かの方法で素人でも簡単に評価額の適正性を確認できる手法がありますか。 |
 |
1.鑑定評価書の審査機関はあるか? |
調査報告書の様式
 |
鑑定評価書提出後に地積の変更が生じたため、依頼者より変更後の地積での対応を求められております。 地積が変わっても鑑定評価の単価は変わらず、総額のみが変更になる場合、鑑定評価書の再依頼を求める必要があるのでしょうか。それとも、変更による影響を記載のうえ、意見書による意見価格として対応することに問題はありますでしょうか。 |
 |
鑑定評価の基礎となる条件ならびに鑑定士の判断が変わるわけでもありません。鑑定評価書の活用を促すアフターサービスと言え、柔軟な対応をすることで差し支えない、と考えます。 |
価格等調査ガイドラインの適用範囲外の業務に係る依頼書等
 |
価格等調査ガイドラインの適用範囲外の業務であるコンサル対応の依頼書や、レポート書式のひな型、作成上の基本規程等はありますでしょうか。 |
 |
本会では、現時点で明確な規定がございませんので、鑑定業者で独自に作成いただきたくお願いいたします。 |
公売時における鑑定評価の徴求
 |
公売時に鑑定評価を依頼せず、固定資産評価格や相続税路線価を参考にして独自に価格決定することは法律に抵触しますか。「不動産鑑定評価に関する法律」やその他の条例や判例等で鑑定評価書を徴収しなければならないという規定はありますか。 |
 |
お問合わせのとおり「不動産鑑定評価に関する法律」その他関連法令等において、公売時に鑑定評価書を徴求しなければならないという規定は、現時点で存在しません。 |
副本の署名押印
 |
提出された鑑定評価書の副本に署名押印しかありません。正本と一致した内容の評価書として取り扱って問題ないですか。副本への署名押印について協会での取り決め等があったら教えてください。 |
 |
鑑定法及び本会の定める指針等に副本への署名押印義務は定められておりません。 |
鑑定士の説明責任
 |
2者共同依頼の調査報告書について、一人の依頼者が内容に疑問が生じたため、作成した鑑定士に内容の説明を求めたところ、鑑定士から、調査報告書の開示先(もう一方の依頼者の弁護士)が拒否しているため説明ができないとの回答があった。 開示先の拒否を理由に鑑定士が依頼者に対する説明を拒絶することが可能なのか。 |
 |
不動産鑑定評価基準「第1章 第4節 不動産鑑定士の責務」に、「依頼者に対して鑑定評価の結果を判り易く誠実に説明を行い得るようにすること」が明記されています。 |
依頼者以外への鑑定評価書の提出先等への提出方法
 |
1.鑑定評価書の依頼者以外の提出先・開示先への提出方法について教えてください。 |
 |
(1)開示は受け取った鑑定評価書を依頼者側が提示又はコピーすることでよろしいでしょうか。 また、依頼者から製本した鑑定評価書をコピーするには、きれいにコピーできないので、当社の控えをPDFで頂きたいと話がありましたが、当社の控えをPDFで依頼者に提供してよろしいでしょうか。
上記の回答のとおり、依頼者以外の者にコピーを渡す、或いはPDFを渡すという行為自体は「開示」に該当します。当該コピーまたはPDFの利用目的が依頼者自身の利用である、或いは鑑定評価書の「開示先」に記載されている者へ渡すことが目的であれば問題はありません。 その他の者に渡す目的での申し出の場合は、「開示」の承諾を得てください(上記1.の回答と同義となりますが念のため申し添えます)。 (2)提出は提出した鑑定評価書の副本を依頼者以外の方に渡すことでよろしいでしょうか。 提出とは、依頼者以外の者へ鑑定評価書の正本または副本を提出することです。 (3)提示及び開示の場合、特に黒く塗りつぶすところはあるでしょうか。 個人情報保護法との関係等、依頼者と内容を十分吟味・協議の上、個別の案件内容に応じてご自身で判断願います。 |
裁判鑑定の依頼
 |
裁判所から、鑑定士個人指名で裁判鑑定の依頼を受けました。その中で、厳密には鑑定評価基準に則ることができない経済価値の査定を求められています(法令等の要請はないが、関係者全員の合意で一定の用法に基づく特定価格的なものを査定してほしいとのこと)。 |
 |
令和3年6月公表の「裁判のための鑑定評価等に関する研究報告」をご参照ください。 |
宅建業を兼業している際の価格査定書
 |
不動産鑑定業と宅建業を同じ事務所(法人)で兼業している場合において、宅建業者として売買の相談を受ける場合、価格アドバイスや無料査定書の発行をする必要があると思います。この場合に発行する無料査定書は不動産鑑定業の鑑定業務の範囲に入るのでしょうか? |
 |
宅建業者の価格査定書は、仲介・媒介契約を目論む業者が自分の示す価格についての説明資料として顧客に提供するものであり、仲介を前提として行う業務です。報酬を得て行う評価ではないため鑑定業務の範囲には入りません。 |
裁判に係る自己のための意見書
 |
自分のためにする裁判で、価格意見書を作成する場合、業者名を入れず、鑑定士の資格を付けて鑑定意見書とすることはできますか? |
 |
自己のためにする意見陳述は、「業として価格等調査を行う場合」にはあたらないと考えられるため、価格等調査ガイドラインの適用外と思われます。 |
電子署名付PDF
 |
電子署名付PDFを正本とする場合についての質問です。 |
 |
電子署名法に則ったシステムを活用し交付することを前提と致します。 |
鑑定評価業務の下請法の適用
 |
不動産の鑑定を受託した不動産鑑定業者(資本金1000万円超)が別の不動産鑑定業者(資本金が1000万円未満)へ鑑定業務の一部を委託(委任)することは下請法に該当するでしょうか。 |
 |
不動産鑑定評価業務は民法上の委任、請負に関係なく、下請法の役務提供委託に該当し、親事業者が資本金1千万円超、下請事業者が1千万円以下の場合には下請法の対象となります。 |
割印の必要性
 |
令和3年9月8日付「鑑定評価書の押印廃止に係る対応について」で押印義務が廃止された旨が通知されたが、正本及び副本に対し割印の押印が望ましいとする連合会からの通知があることから、当該割印の押印についてどう対応すべきか明確にしていただきたい。 |
 |
鑑定評価書への割印が推奨される理由は、鑑定法第39条第3項の鑑定評価書の保存に際し、交付した評価書と保存した評価書が同じ内容であることを証明し(真正性)、改ざんを防止する手段として、割印が有用であるからです。 |
価格等調査ガイドランの適用範囲
 |
電力会社様から、「送電線・電柱等の電気供給事業に関する施設用地の買収のため、買収対象地の価格を第一段階として A 41から2枚程度の意見書で提出いただき、買収交渉が進捗した段階で正式な「不動産鑑定評価書」でいただきたい」というご要望をいただきました。 |
 |
買収対象地の価格(単価であったとしても)を表示する行為は、「不動産の価格等を文書等に表示する」ことと考えられますので、価格等調査ガイドラインが定義する、「価格等調査業務」に該当すると考えられます。 |
PDF化後の紙の処分
 |
1.鑑定評価書の紙の保存について、 PDF化後は紙を処分してしまってもいいのでしょうか。 |
 |
1.鑑定法に基づく鑑定評価書の保管は、 PDF等の電磁的記録で行うことができます(e文書法第3条)。 |
価格の併記
 |
鑑定評価の実務のうち、調査報告書の記載方法についてご教示ください。 |
 |
価格等調査ガイドラインに沿った記載がなされていれば、1つの成果報告書で異なる想定条件の価額を併記しても問題ありません |
反社会的勢力が居住する不動産の評価
 |
貸家及びその敷地(複数戸で構成される賃貸マンション)について、賃借人の一人に反社会勢力の者がいる場合、当該複合不動産の鑑定評価業務を受注することは可能でしょうか。 |
 |
鑑定業者が反社会的勢力と取引を行う訳ではありませんので、鑑定評価を受任しても問題ないものと思料します。 |
利害関係
 |
弊社では、宅建業と鑑定業をあわせて行っております。 |
 |
不動産鑑定評価基準では、下記のとおり利害の有無にかかわらず公平妥当な態度を保持することを要求しておりますが、利害関係があることをもって鑑定評価を禁止している訳ではありません。 |
利害関係
 |
「関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等」についてのご質問です。 |
 |
不動産鑑定評価基準では、下記のとおり利害の有無にかかわらず公平妥当な態度を保持することを要求しておりますが、利害関係があることをもって鑑定評価を禁止している訳ではありません。 |
評価書の保存
 |
鑑定評価書等の保存について |
 |
保存書類を紙面等で別途保存してある場合、PC内の情報を削除しても問題ないと考えます。 |
報告書審査チェックシートの使い方
 |
「成果報告書チェック項目等(本文)(2)」16/18ページにおける、③試算価格の調整にて、「以下を項目立てて記載する。」と記載があります。
これは各試算価格の再吟味の6項目、各試算価格が有する説得力に係る判断の2項目について、評価書にそれぞれ項目を立てて必ず記載しなければならないという趣旨の記載でしょうか。
|
 |
お考えのとおり、項目立てて記載することは必須ではなく、各項目を十分に勘案、考慮して適宜記載すれば良いと考えます。 |
価格等調査ガイドラインの適用範囲(私的鑑定のための成果報告書)
 |
近時、不動産評価に争いのある紛争において、相手方当事者から、「国家資格を有する不動産鑑定士の正確性の評価である」といった主張とともに、不動産鑑定評価基準に則していない「調査報告書」が示される例が散見されます。このような調査は、価格等調査ガイドラインⅠ.4.に照らすと、認められないように解されるのですが、いかがでしょうか。
なお、調査報告書自体が法律事務所宛に作成されており、作成をした当該鑑定士が紛争性を確知していないとも思われません。
|
 |
私的鑑定のための成果報告書は証拠資料として提出され、裁判資料は一般に公開されることが原則です。 |
報告書審査チェックシートの使い方
 |
「報告書審査チェックシート(2024年1月更新)」は「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の別紙3「成果報告書等審査項目(例示)」の改訂版という認識でよろしいでしょうか。
または、別途詳細制定(別紙3は存続)という認識でしょうか。
|
 |
「別紙3」は例示であり、掲載のとおりの使用に限定するものではありません。また、報告書審査チェックシートは、利便性向上のため随時更新しており、以前の更新時も含め、その更新によって「別紙3」の使用方法等が変更されるものではありません。 |
電子署名(差し替えの対応)
 |
「不動産鑑定評価書の電子化に関するQ&A」(以降、「当QA」と記載します)の「Q11(差し替えの対応)」では、差し替えを行う場合の対応として、『「鑑定評価を行った日」と「発行日」を新たな日付に変更し、再度電子署名を行う』と記載されています。このうち、「鑑定評価を行った日」については、差し替えを行う原因が価格判断に関することではない場合でも(※)、「鑑定評価を行った日」を変更すべきとのご見解でしょうか。差し替えを行う原因の如何を問わず「鑑定評価を行った日」を変更すべきとのご見解であれば、その考え方をご教示ください。 |
 |
まず、不動産鑑定士は「鑑定評価報告書」を作成し、「鑑定評価書」は鑑定業者が作成します。「鑑定評価を行った日」とは、不動産鑑定士が「鑑定評価報告書」の内容を確定させた日であると考えられます。 ご質問につきましては、不動産鑑定士が作成した「鑑定評価報告書」に変更が生じたのであれば、「鑑定評価を行った日」を変更すべきですし、そうでないのであれば変更する必要はないと考えます。 |
紹介料
 |
取引先に、不動産鑑定士を紹介し、その取引先と不動産鑑定士が契約した場合、不動産鑑定士から紹介料を請求していいか。 |
 |
不動産鑑定業者や不動産鑑定士が依頼者以外の第三者に案件紹介料等を支払うことについて、法律等で禁じる規程は特段ございません。 |
他人鑑定評価書の時点修正
 |
2年前に、違う鑑定士が標準画地の鑑定評価をすでに実施している。土地区画事業でして、今般、新たに保留地が造成された。そこで、当職に、保留地の売り出し価格を決定するために、「2年間分の時点修正の意見書」と「個別的要因格差率に関する意見書」の依頼があった。基礎となる標準画地の鑑定は別の鑑定士が行ったものであるので、このような依頼は断りたいと思っている。 |
 |
ご質問の件に関しましては、業務指針や実務指針等で定めた事項はありません。A鑑定業者が行った鑑定評価に対し、B鑑定業者が時点修正意見を付けた場合、時点修正した結果についてはA・Bとも責任を負わないことになります。 |
過去時点の鑑定評価
 |
依頼日と価格時点の関係について、依頼日が価格時点より後になっている場合は、価格時点を依頼日の後に設定する若しくは依頼日を価格時点より前にしてもらう等していただいたうえで、依頼書の再発行をお願いする等の措置を講じた方がいいのか。 |
 |
過去時点の鑑定評価の依頼があったものと理解しました。
過去時点の評価を行う場合の留意点は下記のとおりです(不動産鑑定評価基準運用上の留意事項) |
電子ファイルの提出方法等
 |
旧・価格等調査ガイドライン及び実務指針等 前改正時の「基準」及び「ガイドライン」に関するQ&A【取-34】 |
 |
PDFを渡した場合は、ご認識のとおり「開示」で整理して問題ありません。 |
依頼者以外(官庁)の情報公開請求
 |
役所からの依頼で、更地の評価書を提出し、一般競争入札形式で公売に付された。その後、情報公開請求があった。評価書のどの範囲まで公開可であるか。 |
 |
下記サイトで記載のとおり、開示請求があった際は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示しなければならないこととされています。こちらを参考に、依頼者と相談のうえで判断してはいかがでしょうか。 |
同一の評価書で複数類型の評価
 |
対象不動産を特定した鑑定評価基準に則らない価格等調査において、自用の建物及びその敷地の価格等調査(価格及び賃料)を行う場合、それぞれ別々の成果物としなければいけないか、必要的記載事項をそれぞれ充足していれば1つの成果物にまとめてもよいか。 |
 |
複数の類型を一つの成果報告書で表現することは実務でも普通に行われており、特段問題はございません。 |
限定価格での鑑定評価
 |
地方自治体が購入を考えている土地が自治体所有地の隣接地であり、この隣接地を買い取れば、併合一体化で増分価値が発生することが明らかな場合、この自治体が当該隣接地を対象地として正式な鑑定の発注を行う場合、限定価格を求める鑑定評価の依頼をしなければならないのか。それとも、解釈の仕方として、対象地が限定価格の要件を満たす場合には限定価格の依頼が可能であり、もし望むのであれば限定価格の依頼も可能といった解釈で正しいのか。 もし自治体側の事情から、当該対象地には正常価格の評価を求めたいといった希望があれば、当該自治体は買い取りを考えている隣接地の価格を正常価格で鑑定評価の依頼発注を行うことができるか。 |
 |
不動産の売買契約は自由ですので、隣接地所有者間売買で等で市場限定が生じる場合であっても、限定価格で取引しなければいけない訳ではありません。 よって、依頼者が正常価格での評価を求めている場合は、正常価格で評価を行えばよろしいかと思います。 |
財務諸表のための価格調査
 |
家族経営と思われる株式会社から、会社を清算して、会社の財産のうち一部を自己所有に移す(会社から社長に売却すると推定)場合の鑑定評価を依頼されている。 |
 |
財務諸表のための価格調査に該当するかどうかは、企業会計基準等(※)を適用して行われる財務諸表の作成に利用されるかどうかで判断します。 |